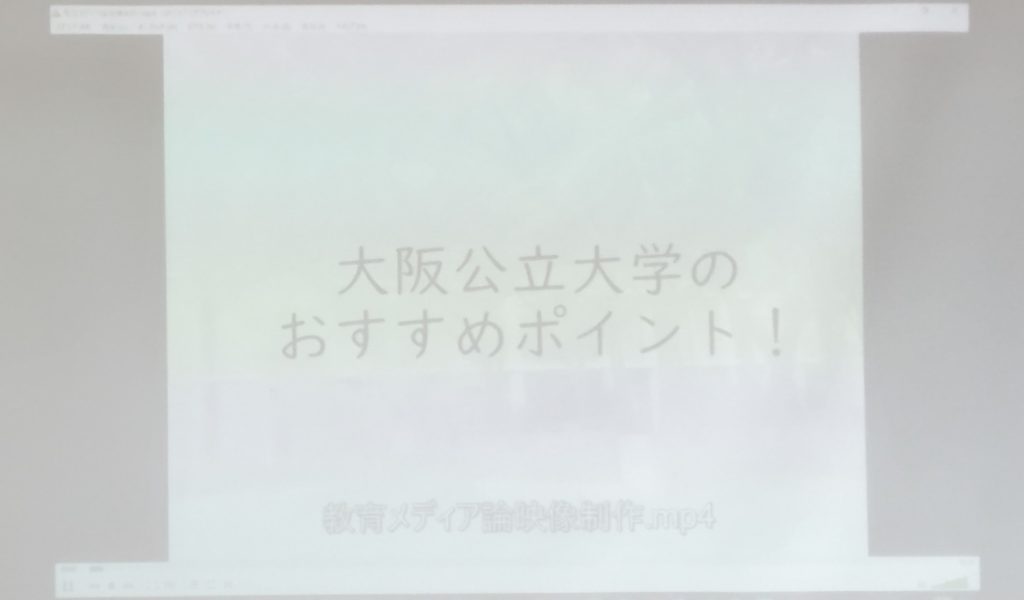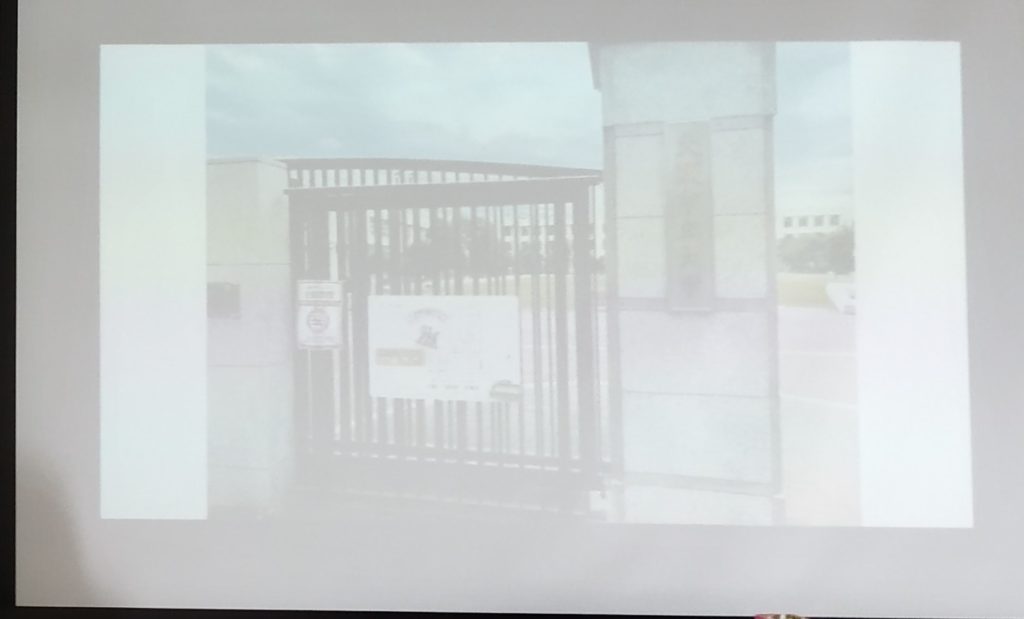大阪公立大学「教育メディア論」集中講義2日目の記録である。
第6回 メディア・リテラシー
メディア・リテラシーの定義からメディアから発信される情報の「批判的な読み解き」とメディアを用いた「創造的な表現・発信」が両輪であることを押さえた。前者に関わって「メディア決定要因」を基に、企業としてのマスメディア、経済的決定要因等を学んだ。
今年度は、生成AIのテーマが大きな話題となっているため、ChatGPTとBingAI、そして画像生成のAIを実例として紹介した。このような時代が到来する中で、いかにメディアからの情報を批判的に検討すべきかについてグループで検討してもらった。ただ、このテーマについては、まだ議論するには情報が十分でなかったので今後の課題となった。
第7回 メディア・リテラシーの視点を踏まえた制作活動
今年度も対面授業で継続して行ってきた映像制作の活動に取り組んだ。まず、「アッ!とメディア」の「送り手の意図を伝える~編集~」を視聴して、グループで課題に取り組んだ。メディア・リテラシーにおける「創造的に表現する」をテーマとして設定したものだった。
第8回 メディア・リテラシーの視点を踏まえた作品発表会(第7回の制作時間に一部充当)
各グループ作成した作品をそれぞれ視聴し、ポイントを評価してもらった。短い時間ではあったが、2グループともそれぞれに工夫点が見られる作品ができていた。
第9回 プログラミング教育
2017年小学校学習指導要領改訂でプログラミング教育が取り上げられたことを紹介した上で、算数・理科と非常に限定的になっていることを共通理解した。それからWhy!?プログラミングを視聴し、Scratchのイメージや問題解決の捉え方を確認した。そして、Scratchでのプログラミングのイメージをもってもらうためにデモとして紹介した。
第10回 プログラミングの実践
第10回は各自でScratchのプログラミングに取り組んでもらったが、「創造性と試行錯誤」をテーマに掲げた。教科に無理矢理当てはめることはプログラミングの本質からかけ離れたものだからだ。